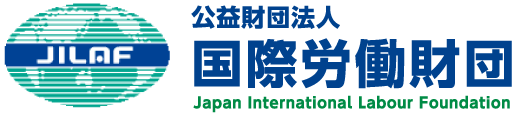2025年 パキスタンの労働事情(ネパール・パキスタンチーム)
以下の情報は招へいプログラム「ネパール・パキスタンチーム」参加者から提出された資料をもとに作成したものである。
参加者情報
- パキスタン労働者連盟 (PUWF)
基本情報(外務省データ2025年7月3日更新分より)
人口:2億4,149万人(2023年、国勢調査)
宗教:イスラム教(国教)
政体:連邦共和制
主要産業:農業、繊維業
GDP:3,765.3億米ドル(2022年、世界銀行)
物価上昇率:19.9%(2022年、世界銀行)
1.参加国におけるホットトピックスと、具体的内容
組織化と組織拡大
1)現状
パキスタン労働者連合(以下、PUWF)は、労働組合への加入や労働組合活動を理由に、使用者から解雇などの不利益な取り扱いを受けることが、労働者が組合への加入に恐怖感を覚えることを問題視している。加えて、労働関係法の実施が不十分であるため、政労使の信頼関係も希薄である。さらに、労働問題を扱う裁判所のプロセスが長期になることや裁判で判決を受けた後、必要な措置が実行されていないことも課題である。ナショナルセンターを統一したPUWFは、加盟組合員を100万人から200万人にすることを目標に据えている。組織化・組織拡大の対象は以下の通り。
-
- 第一次産業を中心に組織化(産業労働団体を設立)
- プライベートセクター(民間組織)の組織拡大
- 産業労働団体を広めることで女性や若者の参画率を向上
- 派遣労働者(派遣元・派遣先)への対応とドメスティックワーカーへの対策
2)改善(戦略)に向けて
PUWFは、労働組合の運動への理解を高めることと、政労使の信頼関係を構築するための運動を実施していく。政府や社会に対して組合の権利を主張し、SNSなどの媒体を通じてPR運動を展開していく。具体的な戦略は以下の通り。
-
- 労働者保護に向けた運動を進めるための裁判制度の充実、検討
- 裁判が長引いた際、労働者(当事者)も賃金が支給されるしくみの検討
- 定年退職後の生活補償(年金改訂・医療保障など)を提起、現在国会で審議中
- SNSを教育ツールとして活用し、男女差別の撤廃と女性と若者の参加促進
対話のメカニズム
1)現状
企業内の労働組合に中央実行委員会を選出、要望を集約し組合員の合意の上、経営側から回答を求める。その後、労使協議(団体交渉)で話し合いを進める。また、回答が得られないケースや協議が不調になった場合、第一段階では裁判となり、裁判所で認める内容を決定する。これに不服の場合、第二段階として、ストライキに移る。更に交渉が不調な場合には、第三段階として、仲裁人(政府で選出、ベテランの裁判官もしくは労働局職員)の解決(最終判断)となり受け入れることになる。
※実例として、パンジャブ州銀行労働組合の事件が発生し、2013年に数人が解雇通告を受けた。その後、裁判に発展、19回の審議の結果、経営側が不服とした仲裁人による解決で職場に戻った。
2)改善に向けて
-
- ナショナルセンターやILOの協力を経て解決し、その前後を通じて不要な対立や新たな紛争に発展しないように進める
- 政労使の解決協議の際、三者構成で労働組合の参加数が低いことから協議への参加を促す
- 三者構成において各側の代表数を対等とすることで、公平な議論の場を確保し、信頼関係の構築と労働運動の強化に繋げる
2)改善に向けて
-
- 時代にあった労働法制を求めるとともにILO批准に向けた運動を推進する
- 労働者の技術や能力を高める活動を展開する
- 雇用形態の多様化に合わせたリサーチを行い効果的な運動を展開する
- 組織的な社会対話を重ね交渉相手に対して協力体制を構築する
- 職場での労使紛争やストライキなどを緩和し社会対話の重要性に傾注す
2.直近に発生した(もしくは発生している)労働争議について
2025年初頭、ネスレ・パキスタンの契約労働者アシフ・ジャット氏が長年の法廷闘争の末に自死(ネスレ事案)。彼の死は、労働制度の機能不全を象徴する事件となり「マズドール・タハッフザ・ムヒム(労働者保護キャンペーン)」の契機となった。
- キャンペーンの目的
-
- 労働法執行体制の強化
- 企業に対する法的、倫理的責任の追及
- 労働訴訟の迅速処理
- 社会保障制度(EOBI含む)の普遍的アクセス確保
- 要求事項(特にネスレ事案に関して)
-
- ネスレなど企業への全面的調査
- アシフ氏の家族への補償
- 労働司法制度の改革
- 第三者契約の厳格な規制
- 長期契約労働者の正社員化
※PUWFは「労働者が正義を求めて命を絶つような社会であってはならない」と訴え、全国的・国際的な連帯を広げながら、抜本的な改革を目指している。
3.労働法制について
- 制度の構造と変遷
-
- 労働法は雇用、労働安全衛生、社会保障、労働者の権利などを包括
- 2010年の第18次憲法改正により労働問題は州の権限
- 各州が独自の法律を施行することで、法的枠組みに断片化と不整合が生じている
- 主な連邦法(現行)
-
- 年産業関係法、、年工場法、年老齢給付法、商店・事業所条例、年社会保障条例など
- 州レベルの主な施策
-
- シンド州:2017年労働安全衛生法、家事・在宅労働者保護法
- パンジャブ州:2019年最低賃金法
- 各州で労働法の近代化が進行中
- 国際基準との整合
-
- パキスタンはILOの36条約を批准
- 主な課題
-
- インフォーマルセクター(労働力の約70%)で法の適用が弱い
- 児童労働、強制労働、在宅・家事・契約労働者の保護不足
- 州間で法的保護に格差がある
- 労働組合(PUWFなど)の提言
-
- 州間法の調和、インフォーマルセクター労働者の保護拡充、三者構成(労使政府)の対話強化
- ILO基準との整合
4.社会保障制度について(主な制度と特徴)
- 従業員社会保障法(Employees’ Social Security Act)
-
- 対象:従業員10人以上の事業所
- 給付:医療、傷病・出産・死亡補償など
- 財源:雇用主が国に定められた最低賃金の6%を負担*。政府負担なし。
- 課題:医療アクセスは、医療施設の非効率や管理不全により妨げられている
*1965年州職員社会保障令(Provincial Employees’ Social Security Ordinance, 1965)第20条より。また、パキスタンでは、本令に基づく社会保障制度が全国的に導入されており、各州が同法をもとに運用を担っている。
- 従業員老齢給付法(Employees’ Old-Age Benefits Act)
-
- 対象:従業員5人以上の事業所
- 給付:老齢・障害・遺族年金
- 財源:雇用主5%、労働者1%を拠出(政府負担なし)
- 課題:登録者は約700万人にとどまる
- 労働者福祉基金(Workers Welfare Fund, WWF)
-
- 対象:労働法で定義される産業労働者
- 給付:結婚給付金、奨学金、死亡給付金、住宅支援
- 財源:雇用主が利益の2%を拠出(政府負担なし)
- 課題:官僚主義と政治的干渉により利用が進まない
- 労働者子女教育条例(Workers Children’s Education Ordinance)
-
- 対象:産業労働者
- 給付:労働者の子供2人までの無料教育
- 財源:雇用主が労働者1人あたり年額100ルピーを負担
- 課題:制度の周知不足と実施の不徹底
- 全体的な課題と問題点
-
- 社会保障制度はフォーマル労働者に限定され、インフォーマルセクター労働者の大多数が取り残されている
- すべての制度で政府の財政支援がなく、雇用主負担に依存
- 制度の運用上の欠陥(制度運営主体監視不足、腐敗、非効率的な管理)により、実効性が低い
※パキスタンでは、州ごとの労働法・社会保障制度の改革が進行中であり、一部の州で労働者保護の拡充や制度の近代化が試みられている。その一方で、インフォーマルセクター労働者の保護、制度の統一、法執行の強化といった課題が残る。PUWFは、三者構成の対話や国際基準との整合を目指し、労働法・社会保障制度改革の議論に積極的に関与している。
現状
2015年制定の憲法により、ネパールは連邦民主共和国として三層の政府(連邦・州・地方)を持つ体制を確立した。憲法施行後には労働法や社会保障関連法が整備され、労働市場の発展に貢献しているが、インフォーマル経済の労働者を制度に組み込むことが大きな課題となっている。
現状
2015年制定の憲法により、ネパールは連邦民主共和国として三層の政府(連邦・州・地方)を持つ体制を確立した。憲法施行後には労働法や社会保障関連法が整備され、労働市場の発展に貢献しているが、インフォーマル経済の労働者を制度に組み込むことが大きな課題となっている。
現行労働法の課題と全国組織の取り組み
2017年の新労働法・社会保障法は、労働組合の長年の活動の成果であるが、社会保障の拡充を勝ち取るために、労働組合は雇用主側の主要の要求でもあった柔軟な雇用形態を受け入れることで太政してた。その結果、ILO基準のの整合性や女性労働者の保護も進んだが、解雇や外部委託(アウトソーシング)が容易になり、団体交渉権やインフォーマルセクター労働者の権利保護は不十分である。NTUCは組合活動を妨げる条項や外部委託の濫用に対して法改正を求めている。
労働法改正の動向
2017年の改正で中央労働諮問会議(CLAC)が設置され、政府・使用者・労働者の三者協議が制度化された。最低賃金も2年ごとに見直され労使が関与。
なお、法令に基づき企業内では労委関係委員会や安全衛生委員会が設けられており、これらの委員会が法制度の見直しにも役割を果たしている。
4.社会保障制度について
現状
社会保障は、失業・病気・老後などにより働けなくなった際に、生活を支える仕組みである。しかし、ネパールでは、社会保障制度の対象が限られており、多くの労働者は十分な所得保障を受けられない。2017年制定の貢献型社会保障法により、インフォーマルセクター労働者にも制度が拡大され、医療や年金・失業支援など多様な給付が提供されている。ただし、保障範囲は選択制であり、包括的な保障はない。2022年には対象者向けの具体的な運用指針も整備された。
課題と全国組織の取り組み
インフォーマルセクター労働者は法制度上に社会保障制度の対象とされているものの、実際の運用面では十分に実現していないため、NTUCはインフォーマルセクター労働者への制度適用を求めて活動しているが、使用者・政府負担の問題や登録制度の不透明さが障害となっている。地方での登録制度の整備や、政府による財政支援の拡充を提案している。
社会保障制度改正の動向
制度は社会状況や必要性に応じて継続的に見直されており、柔軟に改正が進められている
3)対策として
出生率の低下の背景には、出産制度の不備と経済的理由があり、子どもを産まない選択をする家庭が増加している。解消のために以下のような対策が必要。
(1)ILO183号条約の批准ための運動の推進
この条約は、母性保護と母性を理由とした差別禁止、出産休暇(最低14週間)および休業中の所得補償などを規定している(タイと日本は未批准)。
(2)出産休暇の制度統一と有給化
現在、出産休暇の日数や有給休暇は企業によって異なっており、国と企業による有給休暇は合わせても90日間が限度。これを最低でもILO183号条約の出産休暇と同等の98日間を有給休暇として制度化することが必要。
(3)育児休暇制度の整備と拡大
現在、タイの男性を対象とした育児休暇制度は、公務機関に従事する男性を対象にした、15日間の有給休暇(タイでは「奥さん手伝い休暇」と言われている)に限られている。民間企業には適用されていないため、全国民を対象とした育児休暇制度の導入が求められる。
2.不安定雇用について
1)不安定雇用の現状
タイでは、労働組合結成にあたり、一定人数の確保や労働省への登録申請など厳しい法的手続きが求められ、設立のハードルが高い。申請しても許可が下りないケースが少なくない。さらに、労働組合結成に関する活動をした労働者が、使用者から様々な理由によって解雇される事例も発生している。
仮に、労働組合が結成された場合でも、使用者側は団体交渉を拒み、賃金が中々改定されない状態が続いている。そのため、低賃金状態が慢性化しており、また、若年層の採用も抑制されている。結果として、若者の多くは「ギグワーカー」として不安定な雇用形態で働かざるを得ない現状がある。
2)不安定雇用の問題点
(1)労働組合つぶしの横行と交渉の困難性
使用者による労働組合活動の妨害や組合員の解雇が横行しており、労働条件改善に向けた団体交渉の実施が困難となっている。その結果、賃金水準は低く抑えられ、質の高い労働者の確保が困難。結果として慢性的な人手不足を招いている。
(2)非正規労働者の組合加入が法律で認められていない
現行法では、非正規労働者の労働組合加入が認められていない。そのため多くの労働者は劣悪な労働条件の下に働かざるを得ない。
(3)若年層の不安定雇用と賃金格差の実態
20代から30代の若年層が不安定な雇用形態で働いており、賃金水準も低い。法律上は「同一労働・同一賃金」が定められているが、使用者は「業務内容の同一性」や「賃金差の正当性」という独自の解釈を盾にして制度が実質的に守られていない。
(4)組合の継承と技能の断絶
若年層の不安定雇用の増加に伴って、労働組合の継承と持続性が損なわれている。その結果、職場における技能や経験の継承ができないため質の高い労働力の確保が難しくなっている。
3)対策
(1)ILO中核的労働基準条約の批准に向けた取り組み
「第87号条約(結社の自由と団結権の保護)」、「第98号条約(団体交渉権の承認)」について、その批准に向けた取り組みを推進する。そのためには、政治活動を積極的に展開して労働者の声を政治に反映する政治家と連携することが求められる。
(2)ナショナルセンターの統一
現在21あるナショナルセンターの統一を進め、労働者の一致団結を図る。
(3)法改正による組合結成と団体交渉権の保障
労働組合の結成や団体交渉権を明確に法律で保障するため、関連法の改正を求める運動を強化する必要がある。
(4)非正規労働者への労働組合加入権の確保
非正規労働者の労働組合結成と加入を求める活動を展開する。
若年労働者のスキルアップと高度人材の育成は、中国製品を高品質で生産し、新たな製品の開発を促進する上で極めて重要である。しかしながら、全労働人口に占める高度人材の割合は、先進国(40%-50%)よりもはるかに低い7%であり、中国では約2,000万人の高度人材が不足している。特に、若年労働者は「工場で従事することを望まない」傾向にあり、製造業の現場における高度人材の不足は深刻である。
そのような状況において、中華全国総工会は労働技能コンテストの開催や、若年労働者に対する思想・政治的指導の強化を促進してきた。また、オンライン学習プラットフォームを構築・活用し、若年労働者の技術・技能の向上に力を入れている。
2. 労働組合幹部の育成
中華全国総工会による労働組合幹部の教育・訓練活動は、「特色のある社会主義思想を堅持し、労働組合の政治性、先進性、大衆性を維持・強化すること」に重点を置いている。本内容について、3つの側面から概要を述べる。
①組織体系
労働組合幹部に対する教育・訓練業務の主管部門は中華全国総工会組織部であり、教育・訓練の計画、制度構築、監督・監査などの職務を遂行する。下部組織である地方組織は担当地域の労働組合幹部の教育・訓練業務に責任を負う。
②制度
中華全国総工会は5年ごとに1回の全国労働組合幹部教育・訓練計画を制定する。直近では、2024年7月に『全国労働組合幹部教育訓練計画(2024-2028年)』を制定し、今後5年間の活動方針について取り決めた。中華全国総工会と地方組織は毎年年初に年度労働組合幹部養成計画を発表し、労働組合幹部養成の具体的な内容やコース数を取り決めている。2023年以降、オンラインとオフライン合わせて118万人以上の労働組合幹部を訓練した。
③カリキュラムと教材
中華全国総工会は、労働組合の基礎理論、組織活動、広報活動、権益補償、労働と経済活動、労働法制、女性労働者、国際労働運動、産業別別労働組合、中国労働者運動史などについて、2年ごとに、30のカリキュラムと8つの教材を作成している。
3. プラットフォーム労働者の権利と利益の保護
プラットフォーム労働者(約8,400万人)は、国民の多様なニーズを満たし、経済発展に貢献している。
従来の働き方と比較して、プラットフォーム労働者は労使関係が不明確であり、規制がかかりにくい。また、就労地域が広く分散しているため、労働紛争の調査と証拠収集が困難である。
中国はプラットフォーム労働者の権利と利益の保護を非常に重視しており、「新たな雇用形態における労働者の権利と利益の保護に関する指導意見」や「プラットフォーム労働者に関する4つのガイドライン(①労働契約の締結及び書面による合意、②権利利益の保護及び労働報酬、③労働規則の公表、④権利利益の保護に関するガイドライン)」など一連の文書を発行した。