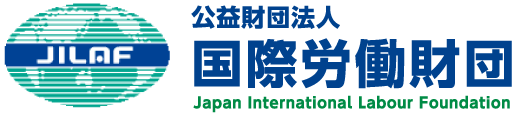第1回国際シンポジウム
2025年7月3日に「ビジネスと人権~変わっていく経済環境をめぐる上流サプライチェーンにおける人権デューデリジェンス:ステークホルダーの役割をいまいちど再模索~」をテーマに、国際シンポジウムを開催し、労働組合関係者、企業、学識経験者など、48名が参加されました。
シンポジウムではインド、スリランカの労働組合代表および経営者団体代表、日本の経営者代表、ILOにご登壇いただき、それぞれからの報告やパネルディスカッションを行いました。
冒頭、JILAF相原理事長とILO駐日代表の富田氏による挨拶を行い、JILAF鈴木副事務長からJILAFの「ビジネスと人件」に関する取り組み及び知り得たことの紹介を行いました。続いて、基調講演として、国際労働機関労働者活動局(ILO ACTRAV)大辻氏から「グローバル・サプライチェーンにおける労働組合の役割」についてご講演をいただました。その後、ビジネスと人権に関する各組織の現状について、各国労使から報告を受けました。また、同テーマに、ILO強靭で包括的なアジアサプライチェーンプロジェクト(RISSC)の本庄氏をコーディネーター、各国報告の講演者、日本経済団体連合会(経団連)の益子上席主幹をパネリストとしてパネルディスカッションを行いました。
各セッションの要旨
基調講演 ILO ACTRAV
代わっていく国際貿易方針によるグローバル・サプライチェーンにおける労働組合の役割と課題を概観し、インフォーマルセクター労働者・移民労働者を含む脆弱な労働者の権利保護を強調している。社会対話を通じたデューデリジェンスや共同モニタリングの推進、国境を超えた労働組合ネットワークの強化が重要である。
各国報告
- インド:労働代表(NTUC、BMS、HMS)
インドのサプライチェーン上流部における労働及び人権課題として、女性やインフォーマルセクター労働者の脆弱性、賃金格差、労働安全衛生上の課題、児童労働や強制労働、環境破壊等の課題が指摘されている。さらに、NGRBC(責任ある企業行動のための国家指針)や国際的枠組み(UNGPs、OECDガイダンス)を基盤とした企業の人権方針策定・モニタリングの強化、労働組合・地域社会との協働を通じ、ディーセント・ワークの推進及び説明責任の確保が求められている。
- インド:使用者代表(ITC)
サプライチェーン上流における人権デューデリジェンスの課題を概説し、賃金不払い、雇用不安定、社会的保護の欠如、方針と実行のギャップといった現状を指摘した。緩和に向けて政府・労働組合・企業の多様なステークホルダーの協働が求められている。
- スリランカ:労働代表(CWC、SLNSS)
スリランカは、紅茶・ゴム産業に従事する労働者に注目し、低賃金、劣悪な居住環境や教育機会の不足、労働安全衛生上の課題、社会的・政治的参加の制約を指摘されている。これらの課題に対応するためには、政府・企業・市民社会の協働による規制の整備、透明性と説明責任の確保が必要である。
- スリランカ:使用者代表(EFC)
アパレル産業を事例として、1971年制定の「労働者雇用契約終了(特別規定)法」に基づく解雇規制が紹介され、雇用主は労働者本人の同意または労働局長の承認を得る必要があると説明される。こうした法的枠組みは、産業競争力を維持しつつ雇用安定と権利保護を確保するものであり、サプライチェーン上流における人権デューデリジェンスの実践とも関連する。
パネルディスカッション
雇用形態の変化や契約労働者・日雇い・プラットフォーム労働者に代表されるインフォーマルセクターの拡大は、人権デューデリジェンスにおける新たな課題として指摘されている。その結果、労働者は労働権教育や法的保護へのアクセスを欠いている。経済環境の変動や「トランプ関税」の影響は、労働者・使用者・政府のいずれか一方が負担すべきものではなく、三者協力による対応が求められている。
解決に向けて労働者・使用者それぞれの立場から各取り組みの説明がある。国内では、労使協議、対話、中小企業を巻き込んだ取り組み、国際レベルでは、労使ネットワークを活用した教育取り組み、多国籍企業(MNEs)への働きかけ等が紹介される。